斎藤慶典『デカルト(哲学のエッセンス)』―理論とは「建築物」か「3本の矢」か?
- 2021.05.05
- 記事
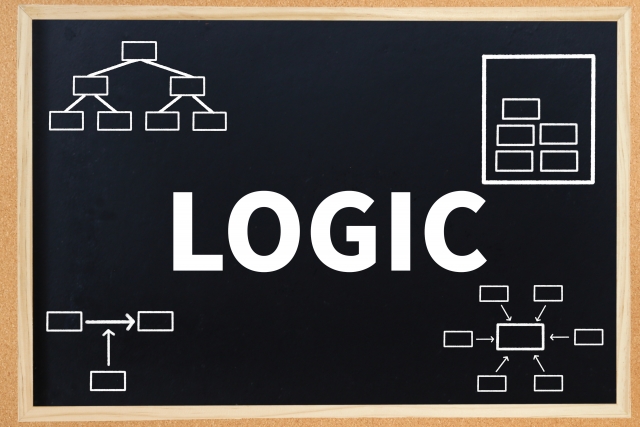
若き日のデカルトは、膨大な読書を通じて過去の偉人との対話を重ねていた。文学、雄弁術、詩、数学、哲学、法学、医学などである。しかし、どれを読んでも彼の知的欲求を完全には満たすことがなかった。彼は最終的に、「おびただしい疑いと迷いに取りつかれてにっちもさっちもいかないありさま」(『方法序説』)に陥った。「本当に疑い得ないもの」とは何なのか?岩盤や粘土層のように諸学問を基礎から支えて揺らがないものとは何なのか?デカルトはそれを追い求めて、書物を捨て現実世界と自分自身と徹底的に向き合うことにした。
「本当に疑い得ないもの」を掘り当てるためにデカルトが編み出したのは、「方法的懐疑」という手法である。「少しでも疑わしいものは真ではない」として退ける(「偽である」と断定するわけではない。偽の可能性が否定できないという意味である)。あらゆるものの中から方法的懐疑に耐えて残ったものこそ、「本当に疑い得ないもの」と呼ぶにふさわしい。
デカルトがまず検討の俎上に載せたのは「感覚」である。我々は日々五感を通じて様々な刺激を受けている。それは我々の身体が確かに受け取った認識であり、疑い得ないのではないか?デカルトの答えは否である。我々は頻繁に見間違いや聞き間違いを犯すから、感覚は絶対ではない。
感覚は誤ることがあるとしても、我々が感覚を媒介として結びついているこの「現実世界」そのものはどうであろうか?世界があることは自明であるように思える。もしこの世界が嘘であったら、我々は今どうしてここに生きていると言えるだろうか?しかし、デカルトは現実世界も疑わしいと断言する。というのも、現実世界は夢である可能性があるからだ。
我々が普段夢を見ている最中に、それが夢であると気づくことはまずない。夢が夢であったと解るのは、夢から覚めた時である。なるほど夢の世界はおかしなことがたくさんあったとしても、夢から覚めて振り返った時にそう思うにすぎないのであって、夢の最中ではそれがたとえ混沌に満ちていようが現実だと信じて疑わない。夢の構造がこのようであるならば、我々が今生きているはずの現実世界も、本当はただ覚めていないだけで、もしかしたら夢なのかもしれない。
では、現実世界を離れて、我々が頭の中で考えている「理念」はどうであろうか?例えば、「美しさ」は1個の理念である。我々が現実的に知覚できるのは美しい花、美しい人、美しい風景といった具体的な事物だが、これらのものは全て現実世界に属しており、前述のようにその現実世界自体が疑わしいとして退けられる以上、個別の事物も阻却される。一方で、「美しさ」という理念そのものは、我々が思考する限りにおいて、それ自体で存在していると考えられそうである。もっと解りやすい例を出せば、現実世界がどのようになっていようとも、「1+1=2」は絶対に疑いようがないのではないか?
ここでもデカルトの答えは否である。ひょっとしたら「欺く神」や「悪しき霊」なるものが存在して、本当は「1+1=2」ではないにもかかわらず、我々の理性を騙して「1+1=2」と思い込ませているかもしれないとデカルトは疑うのである。
感覚も現実世界も理念も方法的懐疑には耐えられなかった。だが、そのようにあれこれと思考している当の私がいることだけは絶対に疑い得ないのではないか?デカルトがいったん出した結論とはこれであった。『省察』では「私はある、私は存在する」と表現されている。「私は考える、ゆえに私は存在する」という『方法序説』や『哲学原理』の言葉の方が一般には有名であるが、この言葉はデカルトの意図を正しく伝えていない。
「私は考える」のだから「存在する」という因果律で結びついているのではない。因果律は理性の働きの一種である。しかし、「理念」の箇所で見たように、理性そのものは欺かれる可能性がある。そのような疑わしいものを差し挟んだ形で、デカルトが絶対的な命題を打ち立てることはない。「私は考える」ことは、端的に「私は存在する」ことに等しい。
もう1つつけ加えるならば、デカルトは「思考すること」を「感ずること」とも言い換えている。なるほど「思考すること」には、対象に向けられた能動性が含まれている。ところが、デカルトが発見したのは、私がそこまで肩肘を張らなくても、自ずと何かを察知してしまうという存在の本質であった。だから「感ずること」という、受動性を含んだ言葉を用いている。
こうして、「ある」=「存在する」=「思考すること」=「感ずること」という等式が成立する。とはいえ、思考することとは理性の働きではないし、感ずることは感覚の働きでもない点には改めて注意が必要である。既に見た通り、理性も感覚も方法的懐疑によって退けられた。私の存在をどのように表現すればよいのかは、非常に難しいところである。およそ言葉というものが理性や感覚の結晶である限り、言葉にこだわること自体が不適切なのかもしれない。それでも敢えて言語化を試みるならば、個人的には「何となく、ぼんやりと意識されてしまうこと」という表現がイメージに近いように感じる。
通常はデカルトの最終到達地点として知られている「私はある、私は存在する」には、実はまだ続きがある。デカルトは、「思考すること」によって拿捕される「思考されるもの」の考察へと進んでいく。デカルトは「思考されるもの」を「観念」と呼び、「本有観念」、「外来観念」、「作為観念」という3種類に分類した。この中で、「思考すること」自身を起源としない観念があれば、それは「他者」の存在を意味する。
「本有観念」とは、「思うこと」のうちに初めから含まれている観念であり、それが何であるかを私(=思うこと)は私自身から直接理解することができる。デカルトは、<もの>、<真理>、<思う>を本有観念の例として指摘している。「外来観念」とは、「思うこと」の外部から、後に与えられた観念である。例えば、私に物音が聞こえ、太陽が見え、火の熱が感じられたとすれば、それらはいずれも私の外から到来したと考えられる。最後の「作為観念」は、私自身によって作り出された観念のことで、妖精たちや竜のような空想上の存在が挙げられる。
「本有観念」はその定義からして「思うこと」を起源としている。「作為観念」も、私自身がその作者であるのだから、私すなわち「思うこと」が起源である。問題は、私の外部からやってくるかのように思える「外来観念」である。繰り返すように、外部の現実世界も、それを私へと媒介する感覚も絶対的なものではない。外部から観念がやって来るというよりも、私の内に既に観念があって、それがたまたま現実世界と一致したにすぎないとデカルトは見る。確かなのは私の内にある観念の方で、夢として破れる余地を残す現実世界ではない。このように考えると、「外来観念」は「本有観念」の組み合わせによって生じるものであり、私の中に起源がある。
デカルトが最後に検討したのが「神」という観念であった。神は「無限性」を特徴とする。神の無限性が際立つのは、私の有限性と鋭い対比をなすからである。私の有限性の中に無限なる観念が与えられているとすれば、そのような無限は有限な私の中のどこを探しても見当たらない以上、私の外にその起源を有することは明らかである。これが、デカルトによる「ア・ポステリオリな(=経験より後の)」神の存在証明である。
神の存在証明には長い歴史があり、「ア・プリオリな(=経験に先立つ)」証明が有名だ。神とは唯一絶対、完全無欠な存在である。もしその存在を欠いているのであれば、神の完全性に背くことになる。したがって、神という観念の中に、一切の経験に先立って、それとは独立に神が存在していると考える。ただし、デカルトはこの「ア・プリオリな」証明を否定する。というのも、神の観念に完全性という特徴を与えたのは理性の働きであり、その理性はくどいようだが騙されているかもしれないためだ。
とはいえ、先ほどのデカルトの説明でも、神の無限性を前提としていた点が私としてはひっかかる。そこでもう少しデカルトの言葉を追ってみると、私という有限をどこまでも拡張させても、決して到達することのない無限を意識せざるを得ないといった文章が見られる。神の無限性は自明、つまり経験に先立つのではなく、私の有限性を極大化させるという経験の後で初めて自覚される。だから、「ア・プリオリな証明」ではなく、「ア・ポステリオリな証明」に分類される。
無限の神は私の外部に起源を有するのであろうか?デカルトは、無限とは本有観念であると言い切る。「思考すること」のうちに含まれる観念なのである。なるほど確かに、デカルトの言う通り、私=思考することの有限性を最大限にまで引き延ばすことによって初めて経験されるのが無限であるならば、無限は私の内部に起源がある。しかし、無限の神は、私の内部に起源があるにもかかわらず、決して私からは理解できない形で、私の外部にある。
神は私にとって特別な他者である。私は神に「触れる」ことしかできない。だが、私が「思うこと」の端的な存立であることは同時に、無限の神に触れることでもあり、両者はコインの裏表の関係にある。デカルトが方法的懐疑の末に到達したのは、このような境地であった。以上が本書の大まかな内容である。
デカルトをめぐっては、しばしば3つの点で誤解されていると私は感じる(私自身もよく誤解していた)。まず、「私はある、私は存在する」という命題における「私」とは、特定の誰かを指しているわけではない。一般的にこの命題は、まるで私という固有の存在だけは絶対的であり、それがあたかも近代啓蒙主義に象徴的なエゴイズムをよく表していると理解される。だが、特定の誰かとは現実世界に属する事象であり、方法的懐疑によって否定された。私とは誰のことでもない。思うこと、端的な存在に対して与えられた仮称にすぎない。
2つ目として、デカルトの合理主義は理性至上主義につながったとされる点も疑ってかかる必要がある。理性が生み出す理念が方法的懐疑によって退けられているからだ。「思考すること」=「感ずること」という等式からもうかがわれるように、デカルトは理性よりももっと感覚的(方法的懐疑によって阻却された感覚のことではなく、端的に感じ取るということ)なことを重視していた。
啓蒙主義は、中世の時代には神の領域に属していた絶対知を、絶対的な理性の働きによって人間のものとし、神を忘却させた。その祖がデカルトだと言われる。しかし、デカルトは神を忘れることはなかった。むしろ、私が有限であることを自覚する限りにおいて、忘れようとしても忘れられない形で、私の外部にぴったりと無限の神がくっついている。かといって、私は神を理解することはできず、ただ触れるにすぎない。こうしたデカルトの極地も正しく理解されていない。
中世までの神に代わって、神と等しい絶対的な理性を持った私という固有の存在が、デカルトのような懐疑論的アプローチで究極の平等を実現しようとすると、暴力的な全体主義を招く(以前の記事「納富信留『プラトン(哲学のエッセンス)』―否定=支配を伴わない新しいUnlearnの形を模索したい」を参照)。全体主義の悲劇は、デカルトの思考を誤解したことで生じる。
万人に同じものを与えるという方法で平等を実現するのは現実的ではない。例えば、世界中の人に米を100kg与えたら平等になるかと言うと、そうではない。ある人にとってはその量は少なく、またある人にとってはそもそも米は必要ではない。したがって、究極の平等は、誰もが何物をも持たない状態を作ることによってのみ達成される。ゼロはどのように比較してもゼロである。懐疑論的アプローチによる否定を通じて、絶対無を実現する。ところが、絶対無を実現しようとしている当の本人は、否定という強力な力を駆使する絶対有の存在である。この点で、極限の平等主義は論理的に破綻してしまう。
ここからは話題を変えて、「解る」とはどういうことなのか、私なりに考察してみたい。本書の著者は冒頭で、「この本はデカルトという死んだものとの間で交わした対話の記録である」といった旨のことを述べている。現代を生きる著者が、既に死んでいるデカルトとの間で対話を交わしたという意味ではない。デカルトが自らの考えを表明した時点で、デカルトという人物は死ぬ。後には「テーマ」だけが残る。そのテーマを著者が「復活」させ、解釈を与えていく。これが「対話」だと言うのである。著者の発想は、デリダの「脱=構築」を想起させる。
確かに、我々が書物を読む時にはこういう態度を取るだろう。作者の人となりなどはひとまず脇に置いて、書かれた言葉とじっくり向き合い、論理の道筋を丁寧に追っていく。我々が熟考するには、作者には死んでいてもらわなければならない。そうでないと、我々が作者の言葉を自由に持ち運んで検討することができないからだ。作者の論理展開が概ね了承された時(完全に了承できることは少ない)、我々は「解った」とうなずく。その論理は時間の制約を超えて通用する。つまり、超時的である。これが「頭」で解るということである。
誰かと直接話をしている時も同様である。相手が言っていることを理解するには、まずは相手の発する言葉に真摯に耳を傾ける。この時点で、話し手とその言葉はいったん切り離され、話し手は死ぬ。会話の場では聞き手が十分に理解できなければ、後から回想したりメモを書き起こしたりしてみて(相手が死んでいるから可能である)、「相手があの時言いたかったことはこういうことか」と納得する。ここでも、話し手の論理は超時的であり、聞き手の理解は頭によるものである。
しかし、これだけで本当に著者や話し手のことを理解したと言えるだろうか?頭で解っていても心がついて行かないという事態は往々にして生じる。心で解るとは、相手の価値観をとらえることである。論理の背景となっている考え方の前提を見出すことである。
論理は少なくとも80%程度の確率で正しいと言えなければならないのに対し、価値観には絶対的な正しさはない。むしろ、反対の価値観を容易に想起できる価値観こそが価値観の名にふさわしい。一例を挙げると、「人を殺してはならない」は論理である。100%正しいかどうか私には自信がないが、社会で広く受け入れられているのは事実だ。一方、「まずは他人を大切にしなければならない」は価値観である。というのも、「まずは自分を大切にしなければならない」という価値観もまた同程度に成立するからである。
頭でも心でも理解するとは、価値観を前提にした論理が成立することが解ることを意味する。単に「他人を殺してはならない」と理解するだけでなく、「まずは他人を大切にしなければならない」から「他人を殺してはならない」と理解することである。あるいは、「まずは自分を大切にしなければならない」から「他人を殺してはならない」と理解することでもある。
一口に価値観と言っても、人生、他者、愛、友人、家族、仕事、遊び、お金、社会、共同体、自然、技術、政治、宗教、国家など、様々なものに対する価値観がある。相手の価値観は、その人と直接接している時、空間を共有している時の言葉の節々、振る舞いの端々に顔を出す。少しずつ、不安定な形で表出する。論理が超時的であるならば、価値観は同時的である。もちろん、後から場面を振り返って、あの人はこんな価値観なのだろうと気づくことはある。だが、価値観の大半は、その場で瞬発的に捕捉される。だからこそ我々は、あの人に共感するとか、逆にあの人のことは気に食わないなどと、直観的に判断を下すことができる。
一般的に、理論とは絶対的な前提に基づき、前提から次の命題を導き、その命題から次の命題を導き・・・という過程を経て結論を得るものだと考えられている。数学が解りやすい例で、100%正しい公理を出発点に様々な証明が組み立てられる。しかし、論理を重ねるうちに徐々に亀裂が走るのが常である。だから、最終的な結論はせいぜい80%程度の正しさしかなく、それゆえに多くの人にある程度受け入れられる一方で、一部の激しい批判も生む。
デカルトは理論を建築術に例えた。そして、建築物を構成する諸要素の1つ1つを疑っては取り除き、本当に疑い得ない岩盤、粘土層のようなものを発見しようとした。本書の著者は、理論とは本当に建築術のようなものなのか?と疑っているのだが、私は別の観点からデカルトの発想を疑ってみたい。つまり、絶対的な前提から出発するのではなく、相対的な価値観から出発する理論の組み立て方、絶対的な前提から命題を積み重ねていくうちに理論の精度が落ちていくのではなく、相対的な価値観を組み合わせていくことで理論の精度が上がっていくという方向性があるのではないか?ということである。
人間に価値観があるのと同様、企業にも価値観がある。通常それらはビジョン(経営理念)に内包されている。何十年にもわたり高いパフォーマンスを上げ続けている偉大な企業は、強固な価値観に基づいた経営を行っていると指摘したのは、アメリカの経営学者ジム・コリンズであった。コリンズの主張で重要なのは、価値観に絶対的なよしあしはないという点である。一般的に、高業績企業は顧客志向の価値観を持っていると思われている。ところが、コリンズがビジョナリー・カンパニーとして挙げているソニーは顧客志向の考え方が弱く、代わりに技術志向が非常に強い。また、タバコがこれだけ世界的に悪者にされつつある中でも、ビジョナリー・カンパニーの1つであるフィリップ・モリスは、タバコの効用を強く信じ、価値観経営の中心に据えている。
私が普段お世話になっている営業研修会社の社長から、最近営業の世界では興味深い変化が起きているという話をうかがった。一昔前までは、御用聞き営業を脱して、顧客企業の課題を解決するソリューション営業が有効だとされていた。ところが、今やどの営業もソリューション提案を行うため、それだけでは差別化できず、結局価格競争に陥ってしまうのだという。
現在注目されているのは、「インサイトセールス」という考え方である(※コロナ禍で進んでいる「インサイドセールス」=内勤営業のことではないので要注意)。単に「御社の課題はこれです。だからこのソリューションが有効です」と提案するだけでは不十分である。顧客企業には頭でその重要性を理解してもらうことはできても、残念ながら顧客企業の心にまでは響かない。これからの営業は、「御社のビジョンはこれです。その実現のためにこのソリューションが有効です」と提案しなければならない。
相対的な価値観を内包するビジョンもまた相対的であるにすぎない。絶対に正しいビジョンなど存在しない。にもかかわらず、顧客企業を取り巻く事業環境や、内部の業務・仕組みを客観的に分析してソリューションの妥当性を説明するよりも、顧客企業のビジョンを下地としてソリューションの妥当性を説明する方が、提案全体の精度が上がる。ここでもまた、デカルトが想定する建築物的な理論構成とは逆の流れが見られる。
もう少し粒度を落とした表現をすれば、「弱いものを束ねると強くなる」ということである。毛利元就が子どもに話した「3本の矢」の教訓が思い起こされる。私はこれまで、シナジーとは足し算ではなく掛け算であり、弱いもの、つまり1を切るものをいくら束ねても、強くなるどころか弱くなる一方だと信じていた。だから、前職のベンチャー企業はグループ企業間でシナジーを発揮できなかったと書いたこともある(前ブログの記事「【ベンチャー失敗の教訓(第11回)】シナジーを発揮しない・できない3社」を参照)。
現在の中小企業診断士としての仕事に関連して言えば、中小企業庁が実施している支援策には、中小企業のグループ化を推進するものが多い。商店街の広域連携、下請製造業の共同販路開拓などが該当する。行政が個社単位ではなくグループ単位にこだわるのは、効率的に支援実績を上げるためだという話を聞いたこともある。
とりあえずグループ化すれば何となくシナジーが現れるだろうと期待するのは、金属材料を適当に混ぜ合わせればやがて金が作れるというまやかしの錬金術に等しいと、以前の私は手厳しく批判したものだ。ところが、もし「弱いものを束ねると強くなる」ということが本当であるならば(商店街や下請製造業を「弱いもの」と決めつけていることには反発もあるだろうが)、グループ化推進施策にも十分な意義が認められる。おそらく中小企業庁も自分ではよく解っていないその意義を、私はもう少し真剣に探索してみようと思う。
-
前の記事

富松保文『アウグスティヌス(哲学のエッセンス)』―「自分を知る」とはどういうことか? 2021.04.21
-
次の記事
記事がありません



