富松保文『アウグスティヌス(哲学のエッセンス)』―「自分を知る」とはどういうことか?
- 2021.04.21
- 記事
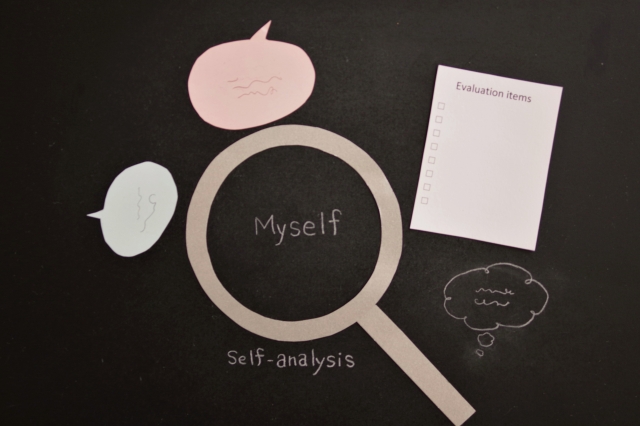
アウグスティヌス(354~430年)は、西ローマ時代に北アフリカで活動した教父である。テオドシウス1世がキリスト教を国教として公認した時期にあたる。ローマ=カトリック教会の理念を確立させ、中世以降のキリスト教に多大な影響を与えた。著書は100冊以上に上るが、代表作は『告白』、『三位一体』、『神の国』である。
本書は、聖書に残されている「コリントの使途への手紙一」という書簡の中の「愛の賛歌」に着目し、次の文章の意味を掘り下げた1冊である。
わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがそのときには、顔と顔を合わせて見ることになる。わたしは、今は一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ、信仰と、希望と、愛、この3つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。
我々が日常生活の中で鏡をのぞき込むと、そこに自分の顔がはっきりと見て取れるのは自明のことである。ところが、「愛の賛歌」では「おぼろに映ったもの」と表現されている。しかし、「そのときには」、「顔と顔を合わせて見る」ことになり、「はっきり知られているようにはっきり知ることになる」と言う。聖書の表現であるから、ここでの「そのとき」とは、キリストが再臨して神の国が実現された時と解釈することができるだろう。
その時に、鏡を介して突き合わせている「顔と顔」とは、私の顔と私の顔なのではなく、私の顔と神の顔ではないだろうか?私は、鏡に映った私の顔を通じて私を知るのではなく、神の顔を通じて私を知るのではないだろうか?
アウグスティヌスは『告白』の中で、「いまや自分自身が、自分にとって大きな謎となった」と述べている。そして、『ソリロキア』という作品の中では、「何を知りたいのか」と自問し、「神と魂を知りたいのだ」と自答する。単に神を知るだけでもなく、魂を知るだけでもない。神を知ることは魂を知ることと一体不可分の関係にある。では、なぜ自分自身を知ることが神への問いをはらんでしまうのか?
この問いに直接答える前に、我々が鏡に映った顔を自分の顔として認識するとはどういうことなのか整理しておきたい。幼児が鏡像認知できるようになる正確な月齢を確かめようとする動きは、20世紀半ば以降に本格化した。ギャラップは実験を通じて、鏡像の自己認知が可能になるのはおおよそ18~20か月だと結論づけた。
松沢哲郎は、鏡映像に対する幼児の反応には、時期に応じて「他者への反応」、「鏡映像の探索」、「自己認識」という3種類があると指摘する。「他者への反応」期は、鏡像を注視し始める4~5か月頃からスタートして、鏡像に笑いかけたり触れたりする6~8か月で頂点に達し、その後こうした反応は、自己の鏡像認知が可能になる1歳半までに急速に消える。「鏡映像の探索」は12~14か月を頂点とする時期で、鏡に近づいて後ろをのぞく、鏡像の動きを積極的に観察するといった行動が見られる。また、9か月頃からは尻込みしたり、鏡を避けたりもする。これは18~20か月で頂点に達するというから、時期的には次の「自己認識」と連なっている。「自己認識」は1歳半で始まり、この頃になると探索や回避行動が減少する代わりに、照れたりおどけたり見とれたりといった自己耽美的な行動が現れる。
幼児が鏡映像を自分だと認識できるようになるには、他者の存在が欠かせないようである。ギャラップはチンパンジーを用いて次のような実験を行った。まず、隔離したまま育てた3頭のチンパンジーは鏡像認知を示さないことを確認した。次に、3頭のうち2頭を12週間にわたって同類の仲間と一緒に過ごすようにさせた一方で、もう1頭は引き続き檻の中で隔離したままにした。
再び鏡像認知のテストを行うと、隔離されたままだったチンパンジーは相変わらず自己認知ができなかったのに対し、別の2頭は自己認知ができるようになっていた。ギャラップは、同類の仲間を視覚的に認知したことが、自分自身の認知につながったと分析した。よもや人間の子どもを使って同じ実験をすることはできないが、人間の場合も事情は同じだろうと推測される。
だが、他者を認知することが鏡映像の自己認知にすぐさま直結しているというわけでもなさそうである。というのも、自己認識が可能となる1歳半と言えば、歩行はもちろん、指差しや初語の時期も過ぎ、二語文や三語文も見られるようになっている時期である。つまり、自分自身を他者や物との間の関係でとらえることが既に可能となっている。
心理学者のナイサーは、人が自分自身について情報を得る仕方には、「生態学的自己」、「対人的自己」、「概念的自己」、「記憶された自己」、「私的自己」の5つがあるとした。
最後の「私的自己」とは、「こころの理論」、つまり、人はそれぞれの人なりの信念や欲求を持っており、行為はそうした信念や欲求によって制御されているという素朴心理学的な理解がはっきりとしてくる4歳頃にになって形成される。
「記憶された自己」とは、単に現在のことばかりでなく、過去や未来についても語ることができ、その連続した時間の流れの中で自分自身をとらえることができるような、いわば自伝的な物語を語ることができる「時間的に拡張された自己」のことで、3歳以降に現れ始める。
「概念的自己」はそれよりももっと以前に、10か月頃から形成される。自分と他者が同じ物や出来事に一緒に注意を向けることができ、その他者の注意がまさに自分に向けられていると理解できるようになると、自分を思考の対象として表象的にとらえることが可能となる。
しかし、表象としての自己理解よりもはるかに先立って、自己についての知覚というものはある。例えば大人でも、自分の乗った列車が駅に止まり、たまたますぐ隣に止まっていた列車が動き始めると、まるで自分の列車が反対方向に走り出したような感覚になることがある。我々は周りの環境を知覚することで、同時に自分の運動や位置を知覚している。こうして自覚される自己が「生態学的自己」で、生まれて間もない頃から備わっている。そして、環境と自己とが表裏一体となった関係は、他者と自己との関係にも同じようにあてはまる。これが「対人的自己」である。
ナイサーの分類に従えば、自己の鏡像認知は概念的自己が形成される時期に相当する。ただ、概念的自己が10か月前後から形成され始めるのに対して、鏡像認知はそこから半年~1年ほど遅れる。ナイサーはこの点に触れて、ちょうどこの時期、幼児が失敗するとばつの悪そうな表情をするといった、他人の評価を気にする態度が見られるようになることから、自己の鏡像認知には「評価的自己意識」が大きく関与しているのではないかという解釈を提示している。
私の理解では、「対人的自己」とは「私“が”ある」という知覚であり、他者との物理的・空間的関係を通じて養われる。そしてそれは、外的な物との関係において獲得される「生態学的自己」が基盤となっている。一方で、「概念的自己」とは「私“で”ある」という知覚であり、「○○ちゃんはいい子だね」とか、「○○ちゃん、顔にご飯がついているよ」とか、「○○ちゃん、絵本を片付けないとダメじゃないの」といった他者からの数々のフィードバックを引き受け、自分のものにすることで芽生える。
「鏡映像が自分“で”ある」という理解は、「ほら、○○ちゃんが鏡に映っているよ」と他者から鏡映像を指差しされたり、鏡の前で不思議そうに手を動かし顔を傾げていると、「鏡の中の○○ちゃんは○○ちゃんと同じ動きをするね」と他者から指摘されたりする中で得られる。他者との関係を通じて、単に自分自身を自分として引き受けるのではなく、最初は他者と認識していた鏡映像を自分として引き受けるのだから、鏡像認知は概念的自己の形成より時間がかかるのだと思われる。
このようにして、幼児は鏡に映った自分を自分だと知る。では、ここからぐっと踏み込んで、「私が私を知る」とは一体どういうことなのか考えてみたい。アウグスティヌスの『告白』の主題はここにある。『告白』は、「ミラノでの回心」と呼ばれる、アウグスティヌスがキリスト教へと回心するきっかけとなった出来事が下地となっている。「回心」とは、一般的な理解に従うと「生まれ変わること」である。一方で、フランスの哲学史家であるピエール・アドによれば、「起源への回帰」という意味もあるそうだ。アウグスティヌスの関心は、「私のはじまり」へと向けられていく。それは、徹底的に内向的、内省的になることでもある。
ところが、「私のはじまりはいつか?」と問うて、アウグスティヌスはいきなり行き詰まる。私が生まれた時の記憶はない。もちろん、脳が発達していないから生まれた時の記憶がないと言ってしまえばそれまでである。しかし、仮に生まれた時の記憶が存在するほどに脳が発達していたとしたらどうだろうか?生まれた瞬間のことを覚えている脳は、いったいいつから存在したのだろうか?はじまりを知る存在は、はじまりよりも前に存在していなければならないではないか?この矛盾ゆえに、私がはじまりを知ることは決してない。私のはじまりは時間的に私を超越している。
空間的にも同じことが言える。私を知るとは、端的に言えば私の内側の意識を知ることでもある。では「私の内とはどこにあるのだろうか?」理解を助けるために、私が3次元の空間に球体として浮かんでいると想像してみよう。まるで、玉ねぎの皮を1枚ずつ剥いでいくように、球体の皮を1枚ずつ剥がしていく。原点に近づけば近づくほど、私の内に迫るはずである。
しかしながら、どこからが私の本当の内なのだろうか?原点に限りなく接近して、わずかに私の球体が残存している時、それが私の内なのだろうか?いや、もはやほんのわずかであっても原点に迫る余地がある以上、内とは言えないのではないか?とはいえ、全てを剥いで原点に接触したら、私の内は消えてしまう。よって、私の内をここだと特定することはできない。要するに、私の内も空間的に私を超越している。
時間的にも空間的にも超越している存在は、神しかいない。だから、本当の意味で私を知るとは、神を知ることに等しい。鏡に映し出された顔は、自分の理解を助ける他者なら誰でもよいというわけではない。いや、誰でもない、他ならぬ神でなければならないのだ。
古代ギリシア史を専門とするフランスの歴史家であるヴェルナンは、「個人」のとらえ方について、「狭い意味での個人」、「主体」、「自我あるいは人格」という興味深い3つの分類を提示している。「狭い意味での個人」とは、古代ギリシアで言うならば、ホメロスに歌われている英雄アギレスや立法者ソロンといった、並外れた個人のことを指す。「主体」とは、一人称単数で「私は」と言う時の「私」であり、「主語」と言い換えてもよい。あなたはこう感じ、そう考えるかもしれないが、私はこう感じ、こう考える。他の人とは違う私という個人が意識されており、それは外の世界、他者との関係に向けられている。
これに対して、「自我あるいは人格」とは、閉ざされた内的世界であり、自分自身の人格との向かい合いであり、何かを意識しているというそのことを意識しているような自己意識を表す。
この3分類自体は決して時代の推移に明確に対応しているわけではないものの、少なくとも「自我」については、古代ギリシア(紀元前4世紀以前)にもヘレニズム期(紀元前4世紀~紀元前1世紀頃)にも見られないとヴェルナンは言う。
ヴェルナンによれば、「自我」が現れるのは、紀元2世紀の後半~4世紀にかけてである。ちょうど、ローマ帝国が衰退に向かい社会が混乱する一方でキリスト教が急速に広まり、社会的紐帯を絶たれた人々が自分の存在とは何かと追求を始めた時期である。アウグスティヌスはまさにこの時代に活躍し、「神と向き合う」という信仰を通じた個人の確立を提示した。一般的には、「自我」は近代の啓蒙主義によって生じたと了承されているが、実はアウグスティヌスの時代に早くもその萌芽を見出すことができるのである。
我々は通常、外部環境、とりわけ他者との相互作用を通じて自分自身を知る。そして、自分の強みを発見し、それを活かすことが大切だとされる。だが、強みを活かすだけで本当に十分なのかと個人的には疑問に感じることがある。
20世紀の偉大な経営学者であるピーター・ドラッカーは、エグゼクティブ(経営管理者)は強みに集中しなければならないと繰り返し、組織には人間の弱みをなかったものにする作用があると力説した。例えば、経理に強い専門家は、個人で事業をしている限りでは、本人が苦手とする営業や事務も自分でやらなければならない。ところが、組織化して営業に強い人、事務に強い人を集めれば、本人は強みである経理に集中することが可能となる。組織は強みを持った人材の組み合わせで成り立つという発想は、現在注目が高まっている「ジョブ型雇用」にもつながる考え方である。
だが、社会から要求される仕事がこれだけ複雑化している現代において、各人が自分の強みにだけ専念することが果たしてどれだけ現実的だろうか?仕事に必要な能力のうち、自分の強みが活きるのはごくわずかであり、弱みが制約となる局面の方が圧倒的に多いのではないだろうか?よって、個人は弱みを克服する努力を忘れてはならないし、組織は人材開発への投資を怠ってはならない。そう言えば、前述のようにアウグスティヌスが個人意識を表出させた『告白』という著書のタイトルには、「罪を懺悔する」という意味がある。自分を知るとは、そのまなざしを強みだけではなく、同時に、いやそれ以上に弱みへと向けることでもある。
自分が強みとしている仕事では、何となくであっても成果が出せる。ただそれは、別の見方をすれば、再現性が低いことでもある。反面、自分が懸命に克服した弱みは、そのストーリーを形式知化しやすい。プロスポーツの世界において、最初から才能があり高い成績を残した一流選手が一流のコーチになるとは限らないのに対し、怪我や挫折を乗り越えた選手の方が優れたコーチになりやすいのはこのためである。
どうしても克服できない弱みが残る場合には、それを強みとする他者を頼る。自分が面倒くさいからというだけの理由で他者を頼る場合、我々はややもするとその他者をぞんざいに扱いがちである(外注先をいじめる企業の心理はこうである)。ところが、自分が逆立ちしてもできなかったことをたやすく実行できる人には、自然と敬意が芽生える。弱みと真摯に向き合えば、人は謙虚になれる。このように、人々が弱みに着目することは、社会の知や徳を発展させる上で重要である。
だが、ここでもう1つ別の問題が生じる。我々が自分の強みや弱みを知るのは、他者との相互作用の中で、換言すれば他者との比較の中においてであることが多い。とはいえ、過剰な比較は過剰な競争を生み出し、人々を疲弊させる。
私自身は昔から劣等感が強く、他人と比較しては自分の足りないところに敏感に反応し、深刻な憂鬱に陥る癖があった。中小企業診断士として独立してからも、様々な分野で活躍する診断士と自分を比べては、「なぜ僕はこんな風に成果が出せないのだろうか?」とよく悩んだ。診断士は何かと飲むのが好きで、お酒を交わしながら「自分はこんな仕事をしているんだ」などと語り合う機会が多い。しかし、他人の話を聞いて落ち込むことが容易に予想された私は、そういう会合に出席するのが嫌でたまらなかった時期がある。
比較対象は診断士に限られない。例えば医師と自分を比べては「なぜ僕は他人の生命を救えないのだろうか?」とか、アーティストと自分を比べては「なぜ僕にはクリエイティビティの才能がないのだろうか?」などと、全方位的に比較して精神をすり減らしていた。
随分昔に「鳥取の公立小学校はどんな平等を目指しているのか?」という記事を書いたのだが、私は今でも競争社会を全面的に否定しようとは考えていない。他者との関係で自己を理解することは、「生態学的自己」や「対人的自己」を基盤として成り立つ「概念的自己」が人間の自然な生育を通じて発露する以上避けられないし、「主体」という自己理解のあり方も、社会の自然な発展の結果と言える。しかし、ヴェルナンが「主体」の次に「自我」を設定したように、そして、アウグスティヌスがその移行プロセスを明らかにしようとしたように、他者との比較を超える次元というものを想定することには十分な意義がありそうである。
私は最近になってようやく、他人と比べたがる衝動を少しずつ抑えられるようになってきた。それは、人生を賭けて達成したい自分なりの目標、一言で言うと志がようやく朧気ながら見えてきたからである。今の自分はその目標に向かうことができているかと意識を集中させれば、周囲の人のことはそれほど気にしなくても済む。比較すべきは「現在のあらゆる他者」ではなく、「未来の自分1人」に絞られる。
志の導き方については、前回の記事「内発的アプローチで小規模企業の事業戦略をデザインする~私自身を題材に」で書いた。志は、「自分もしくは他人の成功を他の人にも広めたい」、「自分もしくは他人の失敗と同じ思いを他の人には味わってほしくない」という願いから生じる。左上は「自分の成功」を他の人にも広め「共有」したいという志である。右上は「他人の成功」に「憧れ」、それを他の人にも教えたいという志である。左下は「自分の失敗」を「教訓」とし、他の人を同じ目に遭わせたくないとする志である。右下は「他人の失敗」に「共感」、彼ら彼女らを失意から救おうとする志である。
私の志の最大の源泉は、前職のベンチャー企業での失敗にある。人材育成をテーマとしている企業でありながら、自社の社員育成が十分でなく、グループ全体で最大50人ほどいた社員が、私の退職時には10人あまりにまで減少してしまった。同程度の規模の企業には私と同じ事態を経験してほしくない。そして、“50人の壁”を超えて持続的に成長する企業を支援したいというのが私の強い願いである(以前の記事「ベンチャー失敗事例」シリーズを参照)。
また私は、世界的に大成功した経営学者であるピーター・ドラッカーの思想が若い時から好きである。さらに、最近は中国儒教の重要な経典である四書五経に強く惹かれるようになった。儒教は古くから日本文化と密接な関係にあるし、ドラッカーの経営学は20世紀後半の日本企業の発展に大きく影響を与えた。私は、これらの教えをもっと広く知ってもらいたいと思っている。とはいえ、四書五経もドラッカーも、今の日本にそのまま適用できるとは限らない(先ほども少し指摘した)。現代の社会的文脈の中で再解釈した上で、日本らしい経営学を構築するという、かなり壮大なプランを抱いている。
私の志は、この「教訓」と「憧れ」が結びついたもので、「ドラッカーや四書五経を日本的に再解釈しつつ、中小企業が人材育成を通じて50人の壁を超える方法を創造すること」である(今回の記事では省略したが、前回の記事では「共有」と「共感」についても触れている)。
私が自分の劣等感を乗り越える方法として、上記のように志を設定したのは効果的であった。しかし、今回の記事との関係性で言うと課題は残されている。というのも、自分や他者の成功、失敗とは、客観的であれ主観的であれ、結局のところ他者との比較において決まるものであり、したがって、競争社会的思考、「主体」的思考を完全には脱していないと感じるからである。日本人の文化的特質として、和辻哲郎は人間(じんかん)主義という言葉を、浜口恵俊は間人(かんじん)主義という言葉を用いた。どちらも、他者との間に生きるのが日本人だという意味である。私はまだその精神的宿命にとらわれているような気がしてならない。
個人が他者との比較によって自分の強みや弱みを知ろうとすることが精神を摩耗させるのと同様、企業が競合他社との比較の上にポジショニングを行う経営学の競争戦略論は、働く人をあまり幸せにしない恐れがある。今のアメリカ企業が競争戦略論を乗り越えてイノベーションに走る背景はここに求めることができる。イノベーションについては前ブログの「現代アメリカ企業戦略論」シリーズで整理を試みたことがあるが、端的にまとめると、リーダーが唯一絶対の神に直接アクセスして自らの使命を受け取り、それを世界中で実現させるという普遍化の契約を神と交わし、履行することである。イノベーターは「主体」を超えて「自我」となる。
競争戦略論の大家であるマイケル・ポーターは、最近になってCSV戦略(Creating Shared Value:共通価値の創造戦略)というコンセプトを提唱した。CSVとは、社会的課題の解決を通じて経済的利益を創造することである。しばしばCSVと対比されるCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)は、事業で得た経済的利益の一部を社会的課題の解決に配分するものであり、引き算の発想に立っている。これに対してCSVでは、最初から社会的課題をターゲットとし、従来の経済的利益以上の利益を達成するという足し算の発想を行う。
ポーターだけの責任ではないが、競争戦略論は勝ち負けの世界であるから、弱者を生み出し社会的課題を深刻化させるという難点があった。そのポーターが社会的課題の解決に本腰を入れたというのだから、世界中の経営者や研究者が驚いた。ポーターがCSV戦略で目指しているのは、一言で言えばイノベーションである。
社会的課題は当事者それぞれにとって固有であり、全体で見ると非常に多様である。福祉問題に携わっている方はお解りいただけるだろうが、例えば貧困層は、貧困の度合いが深刻になるにつれて、当事者を取り巻く現状もその原因も細分化される。その多様性、複雑性をOne-to-Oneマーケティング的なやり方で1つずつ地道に解決するのではなく、普遍的な製品やサービスによって一気に解決しようというのがCSV戦略でありイノベーションである。社会が多様であればあるほど、逆説的に高い普遍性が生まれる余地があることは、以前の記事「日本からイノベーションが生まれない根源的理由」でも触れた。
富松保文『アウグスティヌス(哲学のエッセンス)』―「自分を知る」とはどういうことか?
キリスト教圏の国、特にアメリカには、「主体」を超えて「自我」となる、別の表現をすれば、他者との個別具体的な比較関係を超えて神と直接つながって自己を発見し、イノベーションを起こす道が用意されている。翻って多神教国である日本の場合はどうであろうか?仮に、前述の人間主義や間人主義を克服することができたとしても、神仏とつながるとはどういうことを意味するのであろうか?あまた存在する神仏のいずれと結びつけばよいのだろうか?もし自分の好きな神仏を選ぶとしたら、それは他の神仏と比較検討していることを意味し、現実世界の「主体」的発想が神仏の世界に転写されただけとは言えないだろうか?
一神教国において自分を知るとはどういうことなのかは、本書を読んで多少の手がかりが得られた。では、多神教国において自分を知るとはどういうことなのだろうか?真の意味で自分を知ることができた時、他者との関係はいかなるものになるのだろうか?私は前掲の記事「日本からイノベーションが生まれない根源的理由」でも述べたように、日本人がイノベーションを起こす可能性についてはかなり悲観的である。とはいえ、それではあまりに希望がない。日本企業をこのまま暗澹たる競争社会の中にずるずると押しとどめて集団疲弊に至らしめるのか、はたまたアメリカのイノベーションとは異なる第三の道というものを見出し得るのか、これからも思索を続けたい。
-
前の記事

内発的アプローチで小規模企業の事業戦略をデザインする~私自身を題材に 2021.04.07
-
次の記事

斎藤慶典『デカルト(哲学のエッセンス)』―理論とは「建築物」か「3本の矢」か? 2021.05.05




